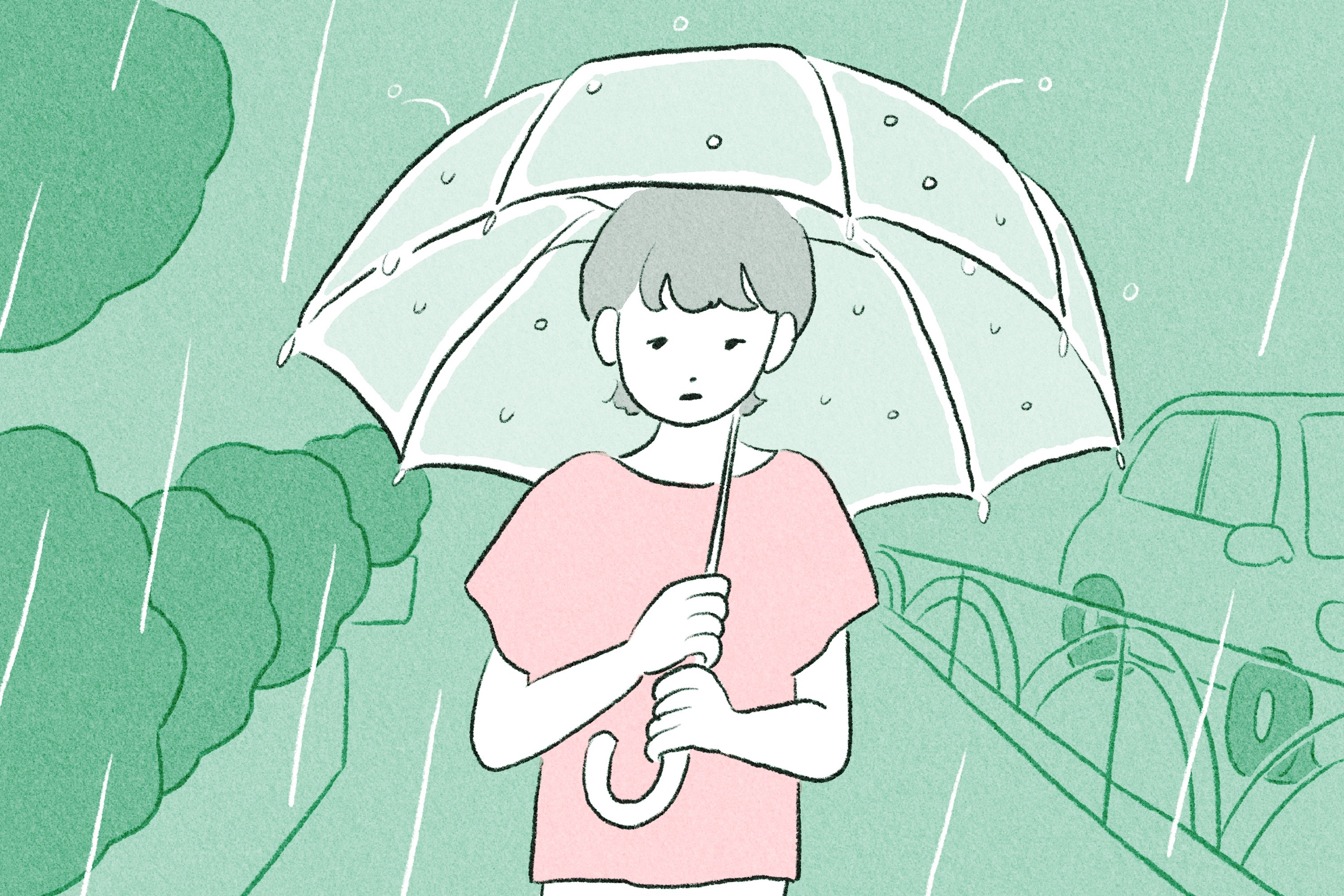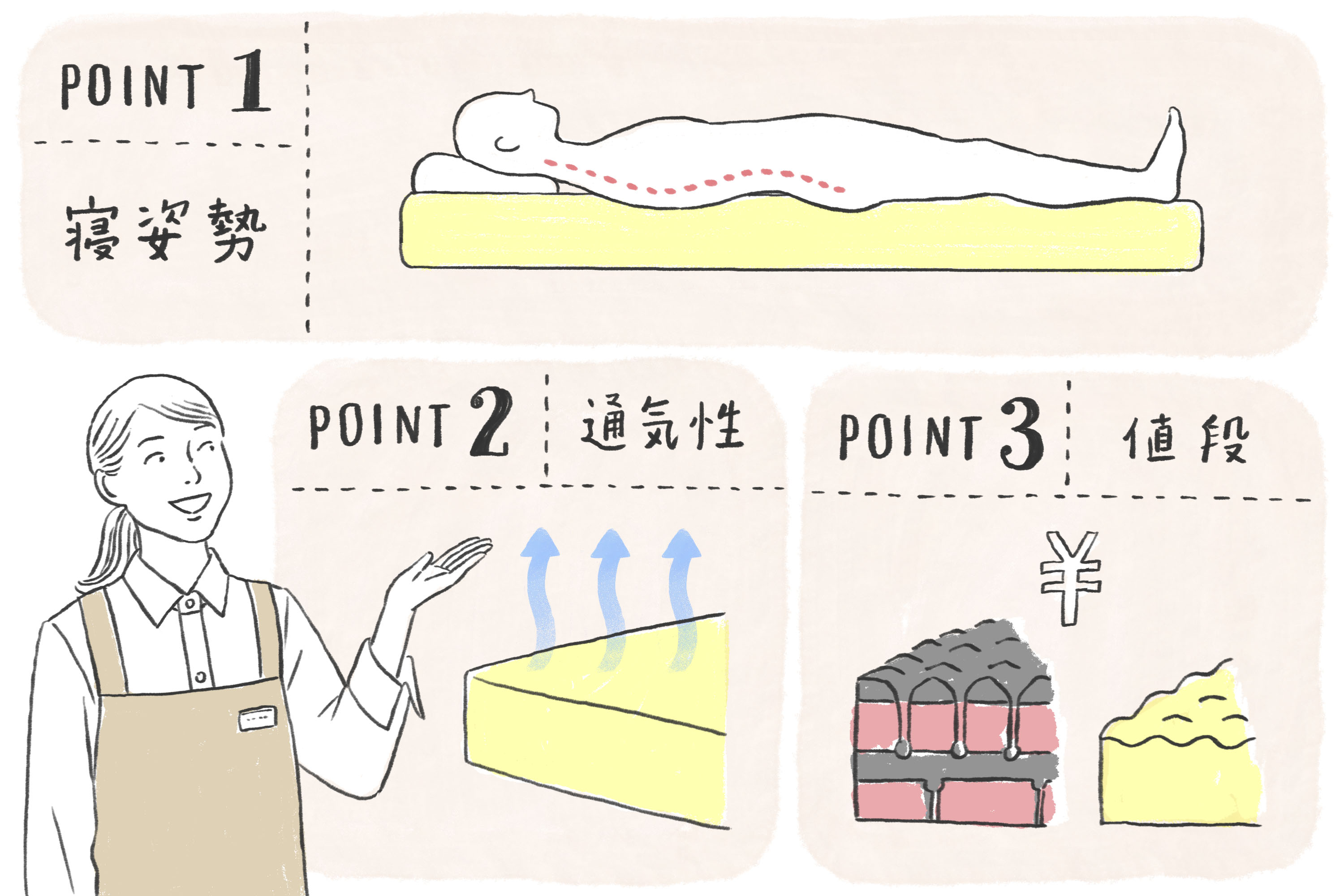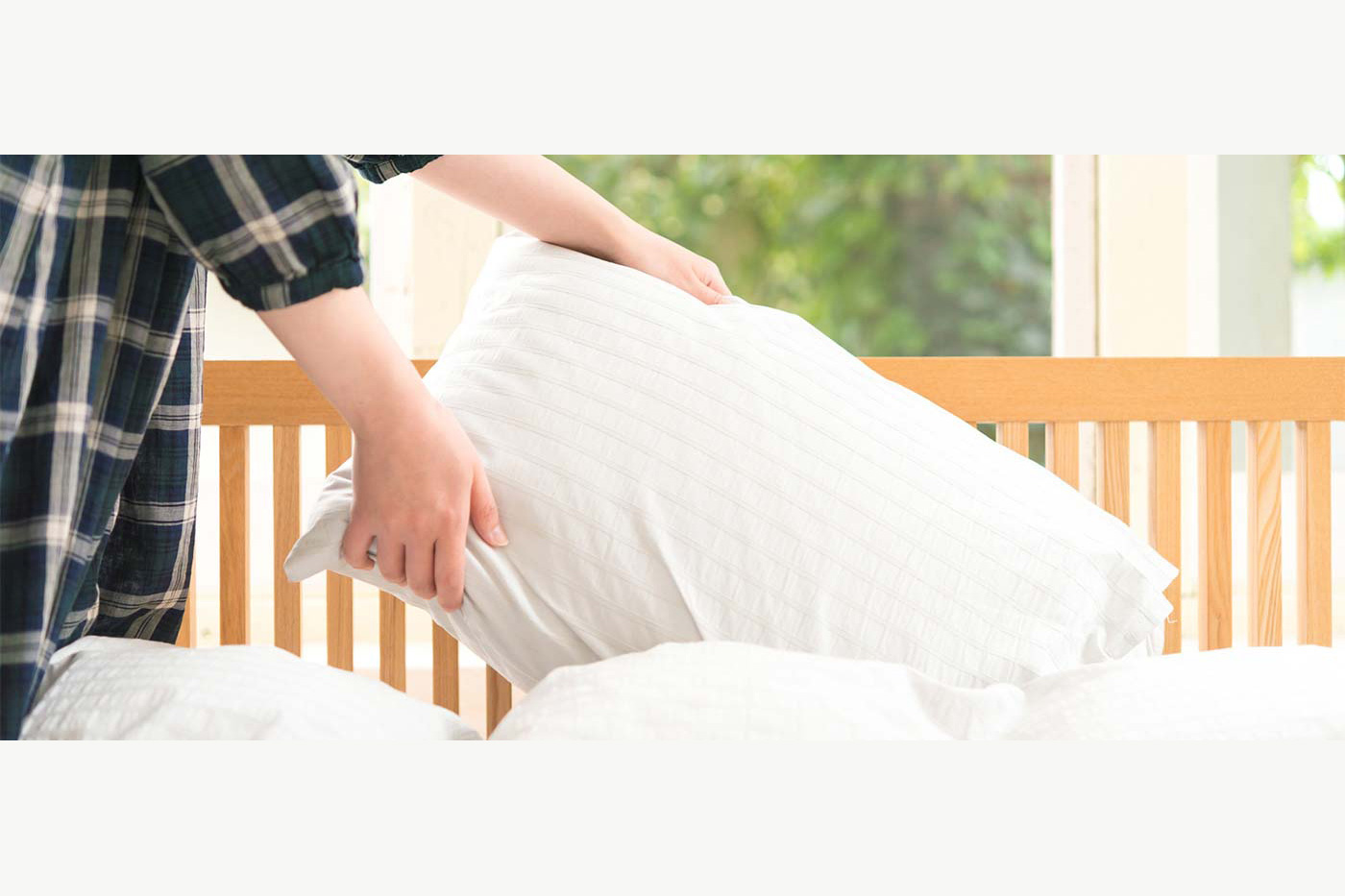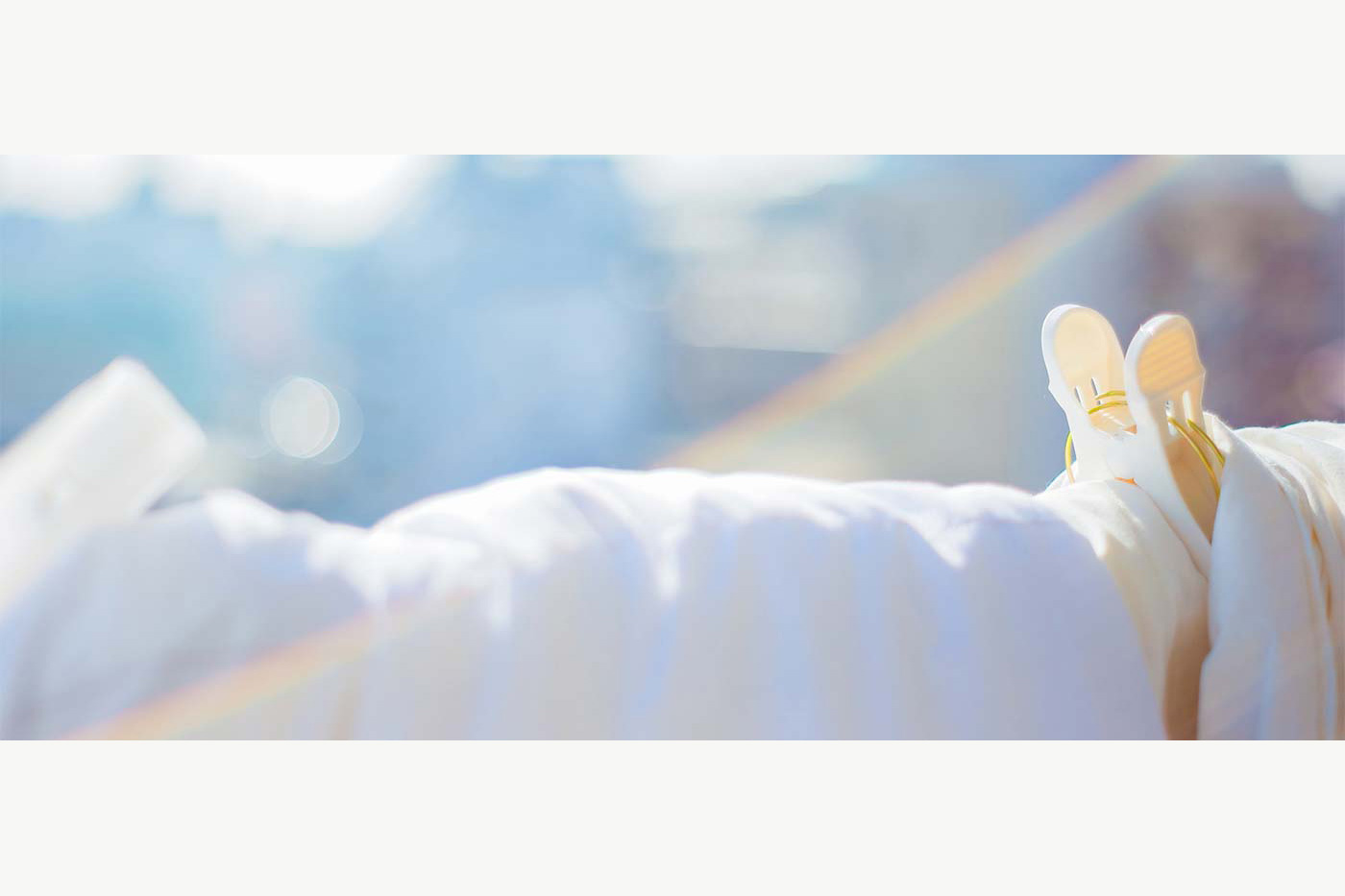カテゴリ:眠り
睡眠の専門医がジャッジ!睡眠に関する雑学、どこまで本当?


インターネットやSNSの浸透により、さまざまな「睡眠の雑学」が世間に広く伝わるようになった昨今。しかし、その情報のすべてが正しいとも限りません。
そこで、日本睡眠学会の総合専門医であり、睡眠の面から心身の健康をサポートする『青山・表参道 睡眠ストレスクリニック』の院長を務める中村真樹先生が、世間に広まった雑学の真偽をジャッジ。
医学的な見地から正しい知識をお届けします。
また、加齢とともに内蔵機能も低下し、生活習慣病をはじめとする疾患の有病率も高まります。すると、頻尿の症状や高血圧による不快感を原因に、睡眠が浅くなることも。
さらに中村先生は「基礎代謝の低下」も指摘。60歳ごろから基礎代謝が落ち、睡眠によって補うべきエネルギー量が減ることから、おのずと睡眠時間が短くなるというのです。
「ただし、睡眠には個人差があり、40代から睡眠の浅さを認識されるケースもあります。特に働き世代の場合、ストレスによる不眠の症状なのか、それとも加齢が原因なのか、判断するのは簡単ではありません。お悩みの方は医療機関を受診するようにしましょう」
中途覚醒・早朝覚醒とは?20代でも多い?夜中に目が覚めるときの予防と対処法を紹介
とはいえ、平日の寝不足を補おうと仕事や学校のない休日に長く睡眠をとる人は多く、長く眠ると「体が軽くなるような感覚を得られる」という人も少なくないはず。
「それは寝だめではなく、過去に積み重ねた寝不足、つまりは“睡眠負債”を返済しているに過ぎません。お金と違い、睡眠は未来に向けた貯蓄は不可能。平日に積み重ねた睡眠負債を休日の長時間睡眠で補おうとしていては、いつか破綻しかねません」
過去から積み重ねた睡眠負債をすべて返済し、健康的な毎日を送るためには、やはり、日常的に適切な睡眠時間を確保することが大切。しかし、それが難しいのも実状です。
「現代社会では、たしかに睡眠負債を抱えがちです。ただし、休日の長時間睡眠はソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)を招きかねません。そのため、休日の朝寝坊は1〜2時間程度に抑え、お昼寝をする場合も10〜20分程度にとどめましょう」
中村先生の指摘するソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)とは、平日と休日の睡眠時間に差が生じることを原因に、まるで時差ボケのような不調を来すこと。
主な原因は休日の長時間睡眠にあるため、平日より長めに寝るにしても、節度が必要というわけです。
不規則な眠りが原因?身体の不調やメンタルにも影響を及ぼす「社会的時差ボケ」を徹底解説

つまりは、後天的な努力によって、なれるものではないのです。
「また、ショートスリーパーの人には目覚まし時計なしに自然と起きられる、仮眠や昼寝をしない、周囲から『眠そうだね』と言われたことがないなど、短い睡眠時間のほかにも複数の特徴があります。これらの特徴すべてを網羅している人は、そうはいません」
事実、カリフォルニア大学の研究グループが2019年に発表した論文よれば、ショートスリーパーの発生頻度は10万人に約4人。この発生率にも遺伝子の配列が関係しており、ショートスリーパーの人は「短い睡眠時間でも健康を損なわない」という報告もあるそうです。
しかし、ショートスリーパーでない人が睡眠時間を削り続ければ、心身に不調を来しかねません。そして、その不調が日中のパフォーマンス低下を招き、本末転倒の結果に。
睡眠時間が短く済めば、仕事も勉強もはかどる——。
そう考える人もいるかもしれませんが、「アマゾン創業者のジェフ・ベゾスは睡眠時間を削ったことによる悪影響を認識し、現在は8時間睡眠を公言しています」と中村先生。やはり、無理は禁物なのです。
理想の睡眠時間とは?7時間とは限らない?調べ方まで解説
「アルコールには入眠作用があり、嗜む程度ならリラックス効果も得られます。一方、体内でアルコールが分解される過程で発生するアルデヒドという物質には覚醒作用があるほか、アルコールには利尿作用もあります。結果的に、睡眠が浅くなってしまうのです」
また、中村先生は「日本はお酒に寛容すぎるかもしれません」とも指摘。なぜなら、2003年に実施された調査によると、日本は「不眠症状を改善することを目的にアルコールを摂取する人」と答えた人の数が、調査対象となった10カ国のうちトップだったといいます。
同調査では「不眠症状を改善することを目的に医師に相談した」と回答した人の数は10カ国中の最下位という結果に。しかし、寝酒の先にある真実は睡眠の質の低下。日本はお酒に寛容すぎる反面、睡眠に対しては無頓着すぎるのかもしれません。
そうした情報がまことしやかに囁かれている理由について、中村先生は「過去に発表された『ベンゾジアゼピン系薬剤の服用が認知症のリスクを高める可能性がある』という論文に基づくのではないか」と指摘します。
不眠の改善にも用いられるベンゾジアゼピン系薬剤。
中村先生が指摘する論文は2014年に発表され、日本のマスコミにも取り上げられましたが、以降、睡眠と認知症に関する研究が進み、むしろ、不眠が認知症のリスクを高めることが解明されつつあるといいます。
「認知症のなかでも特に一般的なアルツハイマー型認知症の原因は、アミロイドβという物質が脳内に蓄積することだと考えられています。そして、アミロイドβが蓄積してしまう原因は不眠。裏を返せば、しっかりと眠ることがアミロイドβの蓄積を防ぐのです」
一方、「長期服用が認知症のリスクを増幅させるエビデンスはないものの、わずかながら、ベンゾジアゼピン系薬剤が認知機能を低下させる危険性も指摘されています」と中村先生。
しかし、睡眠薬の種類はベンゾジアゼピン系薬剤だけではないとのこと。
睡眠薬に不安のある人は、その気持ちを医師に伝え、ご自身に合った処方を受けることが大切です。
しかし、「さまざまな研究機関から、睡眠時間が長い子どもや就寝時間の早い子どもほど成績が良いという報告がされています」と中村先生。
そして、寝不足や睡眠の乱れは注意力や集中力、記憶力や作業スピードの低下、さらにはミスの増加を招くというのです。
「また、最近では睡眠時間と発達障害の関連性も指摘されています。寝不足は注意力や集中力の低下だけでなく、イライラといった情緒不安を引き起こします。これらは発達障害の症状とも重なるほか、発達障害は都会暮らしの子どもに多く発症する傾向があります」
ビルの灯りが物語るとおり、都会は社会全体が宵っぱり。大人の就寝時間が遅ければ、おのずと子どもの就寝時間も遅くなり、睡眠時間も削られてしまいます。
「とはいえ、子どもは大人以上に長い睡眠時間が必要なため、親が『早く寝なさい』と指導することが大切。私の息子も受験生ですが、22時には就寝するよう約束しています」
「寝る子は育つ」は本当!? 睡眠専門医に聞く「眠りと発育・成績」の関係性
正しい情報だけでなく、エビデンスのない間違った情報も世間に広まっている状況について、中村先生は「インターネットやSNSの普及だけでなく、“睡眠の専門家”を騙り、メディアに登場する人の存在も、誤情報の拡散を助長させているかもしれません」と指摘。
専門家という肩書きには確固たる定義がなく、誰もが名乗れてしまうもの。一方、専門家としてメディアに登場されたなら、一般の人はその話を素直に信じてしまいがちです。
「では、誰の情報なら信じても大丈夫なのか。一つの目安になるのが“日本睡眠学会の専門医”であることです。学会には誰でも入会できますが、専門医として認定されるには医師の経験のほか、症例の報告書提出や記述試験、面接試験も必要だからです」
中村先生も日本睡眠学会の総合専門医ですが、学会に認められた人物かどうかを知るには日本睡眠学会の公式ホームページを見れば良いそう。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

そこで、日本睡眠学会の総合専門医であり、睡眠の面から心身の健康をサポートする『青山・表参道 睡眠ストレスクリニック』の院長を務める中村真樹先生が、世間に広まった雑学の真偽をジャッジ。
医学的な見地から正しい知識をお届けします。
目次
高齢になるにつれ、睡眠が浅くなるって本当?
本当!
なぜなら、私たちの睡眠をコントロールしているのは脳。脳は加齢によって機能が低下するため、脳にコントロールされている睡眠も、加齢とともに質が低下する傾向に。また、加齢とともに内蔵機能も低下し、生活習慣病をはじめとする疾患の有病率も高まります。すると、頻尿の症状や高血圧による不快感を原因に、睡眠が浅くなることも。
さらに中村先生は「基礎代謝の低下」も指摘。60歳ごろから基礎代謝が落ち、睡眠によって補うべきエネルギー量が減ることから、おのずと睡眠時間が短くなるというのです。
「ただし、睡眠には個人差があり、40代から睡眠の浅さを認識されるケースもあります。特に働き世代の場合、ストレスによる不眠の症状なのか、それとも加齢が原因なのか、判断するのは簡単ではありません。お悩みの方は医療機関を受診するようにしましょう」
中途覚醒・早朝覚醒とは?20代でも多い?夜中に目が覚めるときの予防と対処法を紹介
寝だめはできないって本当?
本当!
「充電器をどんなに長く電源についないでいたところで、100%以上の蓄電はできません。それは睡眠も同様です」と中村先生。どんなに長く寝ても、寝だめは不可能なのです。とはいえ、平日の寝不足を補おうと仕事や学校のない休日に長く睡眠をとる人は多く、長く眠ると「体が軽くなるような感覚を得られる」という人も少なくないはず。
「それは寝だめではなく、過去に積み重ねた寝不足、つまりは“睡眠負債”を返済しているに過ぎません。お金と違い、睡眠は未来に向けた貯蓄は不可能。平日に積み重ねた睡眠負債を休日の長時間睡眠で補おうとしていては、いつか破綻しかねません」
過去から積み重ねた睡眠負債をすべて返済し、健康的な毎日を送るためには、やはり、日常的に適切な睡眠時間を確保することが大切。しかし、それが難しいのも実状です。
「現代社会では、たしかに睡眠負債を抱えがちです。ただし、休日の長時間睡眠はソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)を招きかねません。そのため、休日の朝寝坊は1〜2時間程度に抑え、お昼寝をする場合も10〜20分程度にとどめましょう」
中村先生の指摘するソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)とは、平日と休日の睡眠時間に差が生じることを原因に、まるで時差ボケのような不調を来すこと。
主な原因は休日の長時間睡眠にあるため、平日より長めに寝るにしても、節度が必要というわけです。
不規則な眠りが原因?身体の不調やメンタルにも影響を及ぼす「社会的時差ボケ」を徹底解説

ショートスリーパーになれるって本当?
ウソ!
平均睡眠時間が6時間未満の人のことを指す、ショートスリーパー。完全には解明されていないものの、現段階では「ショートスリーパーかどうかは遺伝子によって決まる」という学説が有力。つまりは、後天的な努力によって、なれるものではないのです。
「また、ショートスリーパーの人には目覚まし時計なしに自然と起きられる、仮眠や昼寝をしない、周囲から『眠そうだね』と言われたことがないなど、短い睡眠時間のほかにも複数の特徴があります。これらの特徴すべてを網羅している人は、そうはいません」
事実、カリフォルニア大学の研究グループが2019年に発表した論文よれば、ショートスリーパーの発生頻度は10万人に約4人。この発生率にも遺伝子の配列が関係しており、ショートスリーパーの人は「短い睡眠時間でも健康を損なわない」という報告もあるそうです。
しかし、ショートスリーパーでない人が睡眠時間を削り続ければ、心身に不調を来しかねません。そして、その不調が日中のパフォーマンス低下を招き、本末転倒の結果に。
睡眠時間が短く済めば、仕事も勉強もはかどる——。
そう考える人もいるかもしれませんが、「アマゾン創業者のジェフ・ベゾスは睡眠時間を削ったことによる悪影響を認識し、現在は8時間睡眠を公言しています」と中村先生。やはり、無理は禁物なのです。
理想の睡眠時間とは?7時間とは限らない?調べ方まで解説
寝酒は良くないって本当?
本当!
寝る前にお酒を飲むことを指す、寝酒。お酒を飲むと自然と眠くなり、気持ちよく眠りに就けるようなイメージがありますが、気持ちいいのは入眠時のみ。睡眠全体を見れば、その質を低下させ、寝酒が常態化すれば、アルコール依存のリスクも高まります。「アルコールには入眠作用があり、嗜む程度ならリラックス効果も得られます。一方、体内でアルコールが分解される過程で発生するアルデヒドという物質には覚醒作用があるほか、アルコールには利尿作用もあります。結果的に、睡眠が浅くなってしまうのです」
また、中村先生は「日本はお酒に寛容すぎるかもしれません」とも指摘。なぜなら、2003年に実施された調査によると、日本は「不眠症状を改善することを目的にアルコールを摂取する人」と答えた人の数が、調査対象となった10カ国のうちトップだったといいます。
同調査では「不眠症状を改善することを目的に医師に相談した」と回答した人の数は10カ国中の最下位という結果に。しかし、寝酒の先にある真実は睡眠の質の低下。日本はお酒に寛容すぎる反面、睡眠に対しては無頓着すぎるのかもしれません。
睡眠薬は認知症になりやすいって本当?
ウソ!
睡眠薬を服用すると認知症になりやすくなる——。そうした情報がまことしやかに囁かれている理由について、中村先生は「過去に発表された『ベンゾジアゼピン系薬剤の服用が認知症のリスクを高める可能性がある』という論文に基づくのではないか」と指摘します。
不眠の改善にも用いられるベンゾジアゼピン系薬剤。
中村先生が指摘する論文は2014年に発表され、日本のマスコミにも取り上げられましたが、以降、睡眠と認知症に関する研究が進み、むしろ、不眠が認知症のリスクを高めることが解明されつつあるといいます。
「認知症のなかでも特に一般的なアルツハイマー型認知症の原因は、アミロイドβという物質が脳内に蓄積することだと考えられています。そして、アミロイドβが蓄積してしまう原因は不眠。裏を返せば、しっかりと眠ることがアミロイドβの蓄積を防ぐのです」
一方、「長期服用が認知症のリスクを増幅させるエビデンスはないものの、わずかながら、ベンゾジアゼピン系薬剤が認知機能を低下させる危険性も指摘されています」と中村先生。
しかし、睡眠薬の種類はベンゾジアゼピン系薬剤だけではないとのこと。
睡眠薬に不安のある人は、その気持ちを医師に伝え、ご自身に合った処方を受けることが大切です。
よく眠る子供のほうが学業の成績が良いって本当?
本当!
成績アップのため、寝る間を惜しんで勉強をした経験のある人は少なくないはず。最近では学習塾のニーズは高まり、帰宅が遅くなるケースも多いようです。しかし、「さまざまな研究機関から、睡眠時間が長い子どもや就寝時間の早い子どもほど成績が良いという報告がされています」と中村先生。
そして、寝不足や睡眠の乱れは注意力や集中力、記憶力や作業スピードの低下、さらにはミスの増加を招くというのです。
「また、最近では睡眠時間と発達障害の関連性も指摘されています。寝不足は注意力や集中力の低下だけでなく、イライラといった情緒不安を引き起こします。これらは発達障害の症状とも重なるほか、発達障害は都会暮らしの子どもに多く発症する傾向があります」
ビルの灯りが物語るとおり、都会は社会全体が宵っぱり。大人の就寝時間が遅ければ、おのずと子どもの就寝時間も遅くなり、睡眠時間も削られてしまいます。
「とはいえ、子どもは大人以上に長い睡眠時間が必要なため、親が『早く寝なさい』と指導することが大切。私の息子も受験生ですが、22時には就寝するよう約束しています」
「寝る子は育つ」は本当!? 睡眠専門医に聞く「眠りと発育・成績」の関係性
***
正しい情報だけでなく、エビデンスのない間違った情報も世間に広まっている状況について、中村先生は「インターネットやSNSの普及だけでなく、“睡眠の専門家”を騙り、メディアに登場する人の存在も、誤情報の拡散を助長させているかもしれません」と指摘。
専門家という肩書きには確固たる定義がなく、誰もが名乗れてしまうもの。一方、専門家としてメディアに登場されたなら、一般の人はその話を素直に信じてしまいがちです。
「では、誰の情報なら信じても大丈夫なのか。一つの目安になるのが“日本睡眠学会の専門医”であることです。学会には誰でも入会できますが、専門医として認定されるには医師の経験のほか、症例の報告書提出や記述試験、面接試験も必要だからです」
中村先生も日本睡眠学会の総合専門医ですが、学会に認められた人物かどうかを知るには日本睡眠学会の公式ホームページを見れば良いそう。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

青山・表参道 睡眠ストレスクリニック院長
中村真樹先生
日本睡眠学会総合専門医・指導医。東北大学医学部卒業、東北大学大学院医学系研究科修了後、東北大学病院精神科で助教、外来医長を務める。その後、睡眠総合ケアクリニック代々木院長を経て、2017年「青山・表参道 睡眠ストレスクリニック」を開院。臨床と研究、両面の実績があり、睡眠に悩む多くの患者さんの治療にあたっている。ビジネスパーソン向けの書籍『仕事が冴える眠活法』(三笠書房)も話題に。
https://omotesando-sleep.com/
この記事を見た人は
こんな商品に興味を持っています
眠りの関連記事
人気記事ランキング
おすすめ記事
最近見た商品
この記事に関連するキーワード

この記事が気に入ったら
いいね!しよう