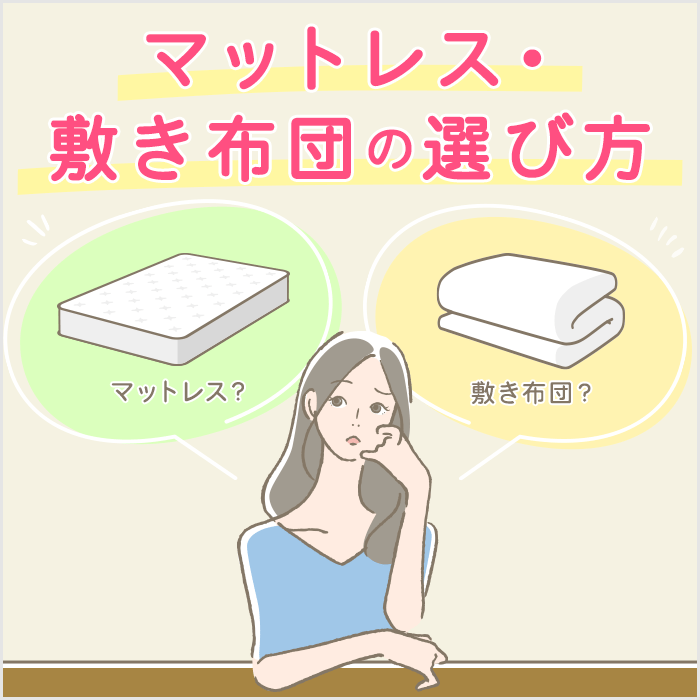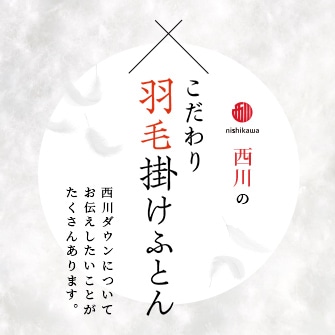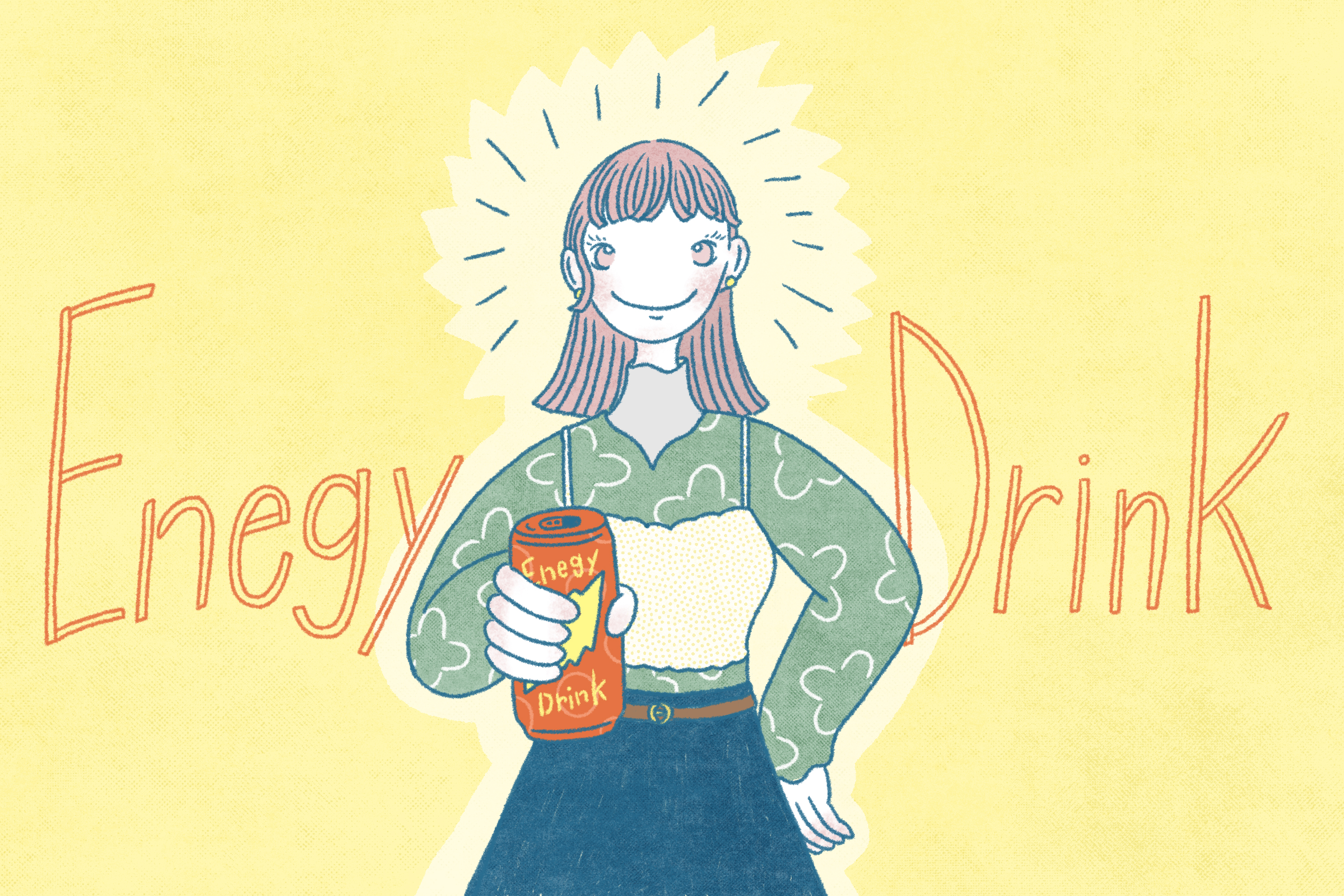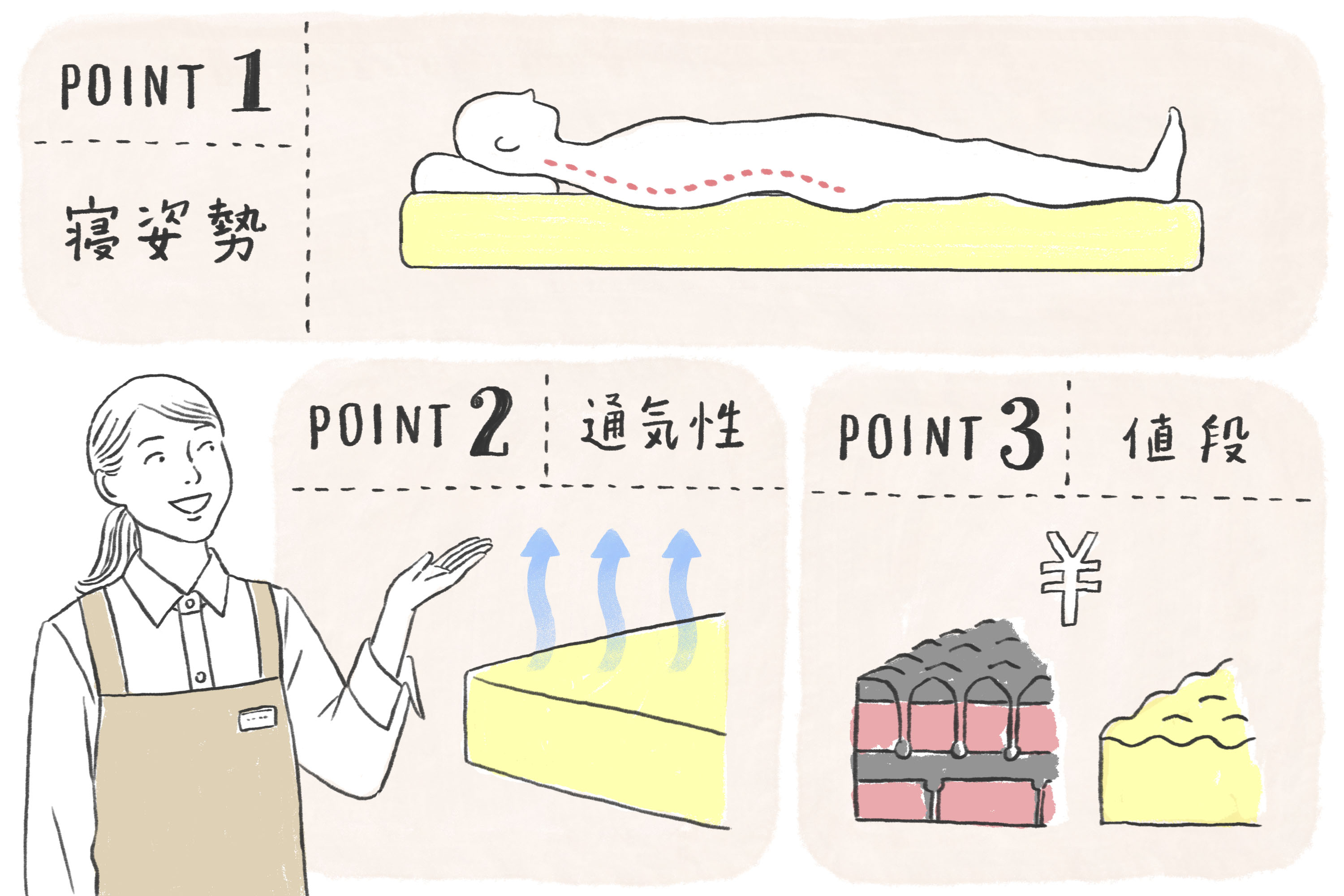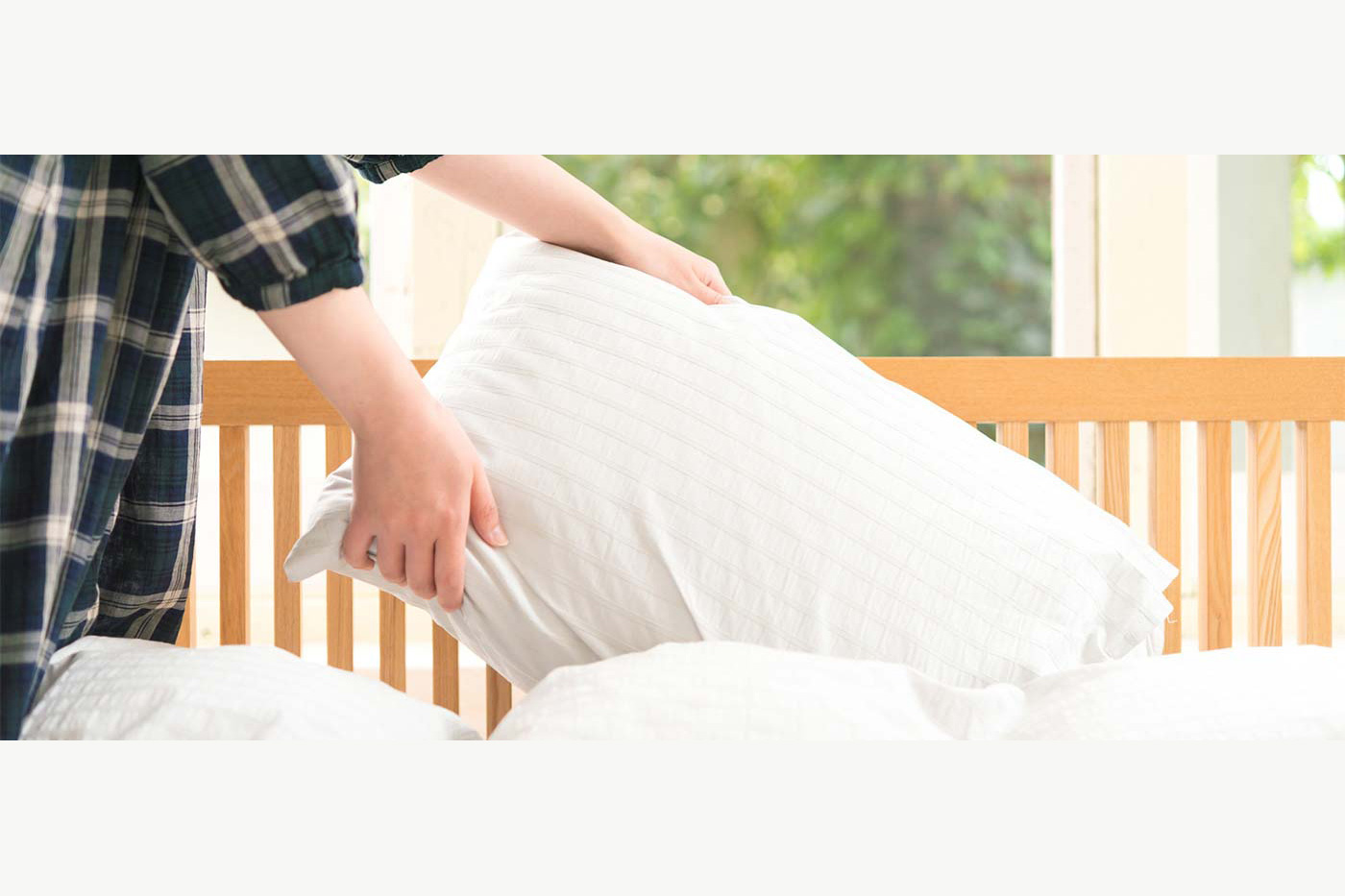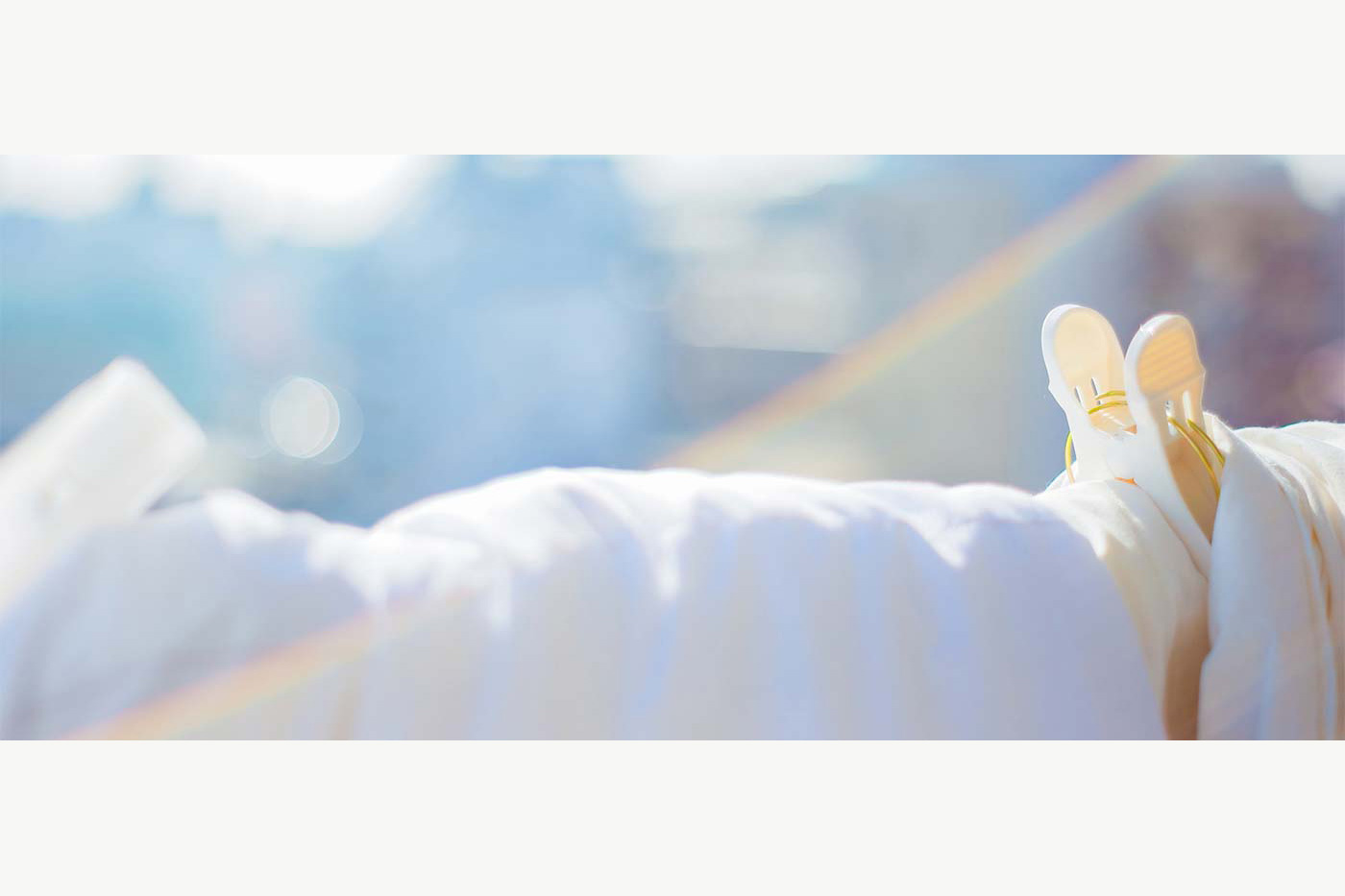カテゴリ:眠り
中途覚醒・早朝覚醒とは?20代でも多い?夜中に目が覚めるときの予防と対処法を紹介

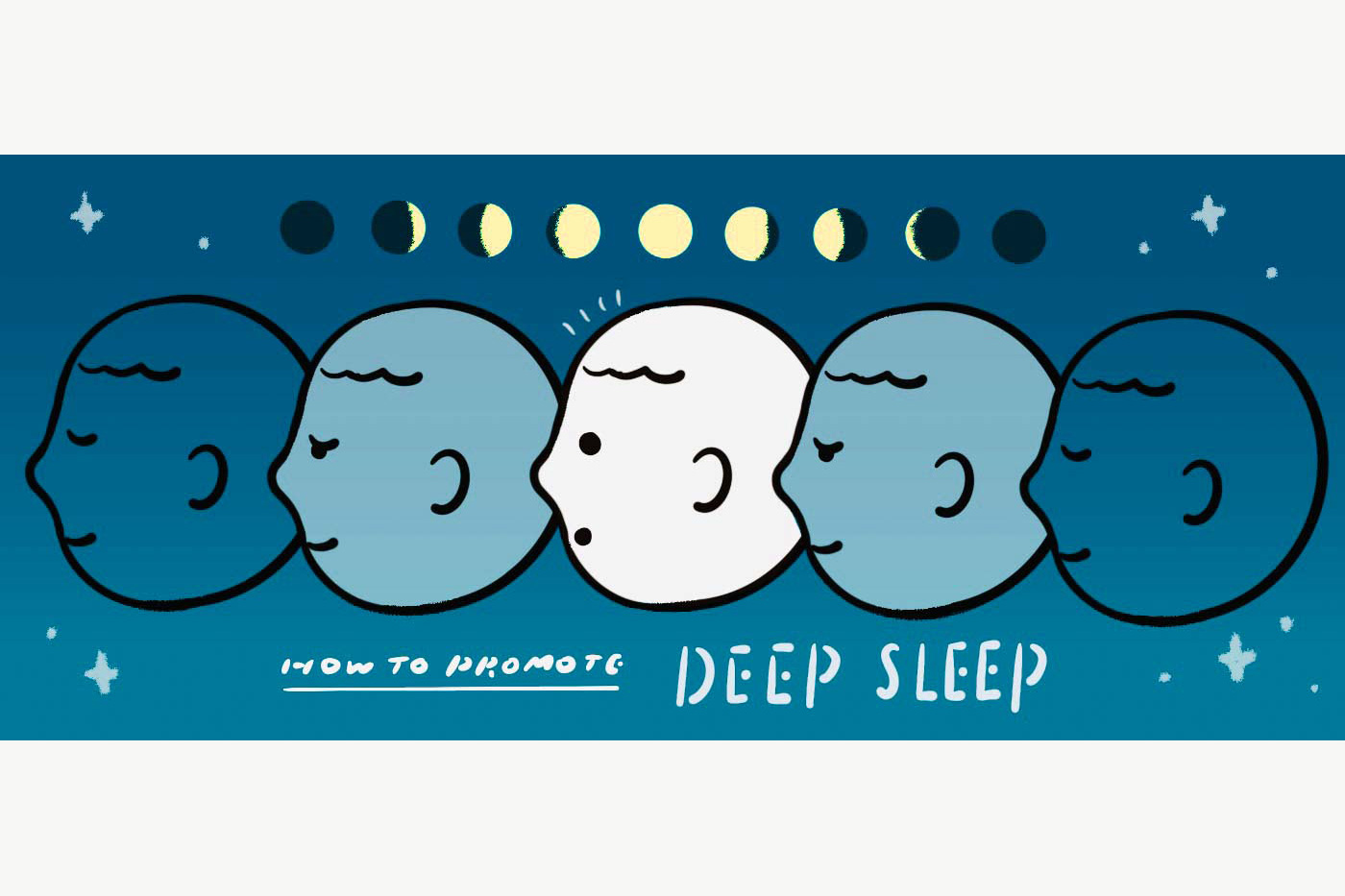
布団に入ってもなかなか眠れない、疲れているはずなのに目が冴えちゃう。そんなふうに、眠れなくてイライラすることってありますよね。
調査によると、布団に入ってから実際に眠りにつくまでの時間が30分未満の割合は78%となっていますが、残り22%は30分以上もかかっていることが分かります。寝入りにかかる時間はそのときの精神状態や忙しさ、体調によっても変化すると言われていますので、寝入りが悪い日に最適の対策があると良いですよね。 一度、眠りについたはずなのに、夜中に何度も目覚めてしまう。普段の起床時間より何時間も早く目が覚めてしまい、それから眠れない。そんな「中途覚醒」「早朝覚醒」は、これまで高齢の方に多いといわれてきました。
しかし、昨今は20〜30代の若者にも増えているそう。中途覚醒や早朝覚醒になる原因とその対策を青山・表参道 睡眠ストレスクリニック院長 中村 真樹先生に伺います。
目次
中途覚醒・早期覚醒とは?
中途覚醒とは、一度入眠したあと、翌朝起床するまでの間に何度も目が覚めてしまう症状のこと。また、早朝覚醒は、通常の起床時間の2時間以上前に目が覚めてしまい、その後、再入眠できないか、入眠できても熟睡できない症状のことです。「ぐっすり眠れているようでも、一晩に数回、ほんの数秒間、脳が目覚めることがありますが、多くの方は一瞬のことなので覚えていません。
しかし、中途覚醒・早朝覚醒は、本人が自覚するくらいはっきり目が覚めてしまっている状態。一度、目が覚めても数分ですぐ眠ることができれば問題ないですが、再度眠ることができなかったり、寝てもすぐに起きてしまったりする場合は、中途覚醒に当てはまります。
中途覚醒・早期覚醒の原因とは?夜中になぜ目が覚める?
中途覚醒と早朝覚醒の原因には、どのようなものが考えられるのでしょうか?
①加齢
まず、主な原因として考えられるのが「加齢」によるもの。睡眠を維持するために必要な脳機能は、加齢によって低下していきます。最近の研究では、40代後半以降、10年ごとに中途覚醒時間が約10分長くなり、もっとも深い睡眠段階である「ノンレム睡眠N3」の時間は約2%ずつ減少していくことがわかっています。また、年齢が上がるにつれて必要とする睡眠時間は短くなります。老年期に必要な睡眠時間は、6〜7時間程度。しかし、必要以上に睡眠を取ろうと長時間布団に入ってしまうと、全体の睡眠が浅くなり、中途覚醒・早朝覚醒が生じやすくなります。
②持病と治療薬の副作用
年齢とともに高血圧や不整脈、糖尿病や呼吸器疾患、夜間頻尿など、さまざまな病気にかかる方が増えますが、これらの病気による不快感により目が覚めてしまうことがあります。さらに、高血圧や喘息などの一部の治療薬の副作用によって、眠りが浅くなってしまう場合も考えられます。
③ストレス
高齢の方だけでなく、若者にも中途覚醒・早朝覚醒が増えている主な理由に、ストレスが挙げられます。環境の変化や、将来や仕事への不安を抱えていると、身体が緊張状態になり眠りが浅くなるのです。④カフェイン飲料、アルコールなどの嗜好品
残業や副業のために夜に「もうひと頑張りしよう」と、眠気覚ましにエナジードリンクやコーヒーを飲む方もいるかと思います。しかし、カフェインの覚醒維持作用は、個人差がありますが、平均して約4時間前後。体内で完全に分解されるまで8時間ほどかかることになるため、寝つきが悪くなるだけでなく、眠りが浅くなり中途覚醒しやすくなります。
また、アルコールにはリラックス効果があるため寝つきは良くなりますが、体内でアルコールが分解され始めると睡眠は浅くなります。アルコールの利尿作用により夜中に目が覚めることもあるでしょう。
⑤不規則な生活・長い昼寝
寝不足や疲労が溜まっていると、その反動でいつもより早く寝つけることもあります。しかし、不規則な生活が続いていると睡眠リズムが不安定になり、寝てもすぐに目が覚めてしまうことも。また、「寝溜め」と称して休日に昼過ぎまで寝ていると、夜の眠りが浅くなり、寝つきの悪さや中途覚醒の原因になります。
不眠そのものがいずれストレスに
中途覚醒・早朝覚醒が数日でおさまるのなら深刻に考える必要はありませんが、週に3回以上症状があり、それが数週間以上続くようであれば不眠が慢性化しているといえます。
「最初は仕事のストレスから眠れなかった状態が、だんだんと不眠そのものがストレスになってしまうんです。『ちゃんと寝なきゃ!』と快眠テクニックを実践すればするほど、快眠テクニックを行うこと自体が義務になり、身体が緊張して眠れなくなります。『やっているのになぜ眠れないんだ』と不安が強まり、ますます眠りが浅くなってしまうという悪循環になるのです」
快眠のためのテクニックは、あくまで就寝前のリラックス方法の1つ。それをやれば必ず眠れるはず、と思うのではなく、自分に合うものを探して、リラックスするための就寝前の習慣にしていく心のゆとりが必要です。
中途覚醒・早期覚醒の予防方法
中途覚醒・早朝覚醒の予防としては、「規則正しい生活」「適度な運動」「ストレスマネージメント」の3つが挙げられます。
①規則正しい生活
良い眠りの条件は「量(睡眠時間)」「質(眠りを悪くする原因の排除)」「タイミング(規則正しい生活)」です。毎日できるだけ規則正しい生活を送ることができればメリハリがつき、夜間はしっかり眠れるようになります。②適度な運動
睡眠の役割の1つに、身体疲労の回復があります。人間の身体は、適度に身体が疲れていたほうが熟睡しやすくなり中途覚醒・早朝覚醒を予防できるといいます。ただし、就寝前に激しい運動をして興奮状態になったり、筋肉痛などの不快感が残ってしまったりすると、逆に不眠の原因になるので要注意。③ストレスマネージメント
不安や緊張が強いと寝つきが悪くなり、寝つけても眠りが浅くなりやすく中途覚醒・早朝覚醒の原因になります。就寝前にヨガやストレッチなど、興奮しない程度に身体を動かしリラクゼーションを。また、休日の日中は、ショッピングや運動、友人に会うなど、ある程度アクティブに動いたほうがネガティブな思考を抱えすぎず、ストレス発散につながると考えられます。
目覚めてしまったあとの過ごし方
では、途中で目覚めてしまったあと、どのように過ごしたら良いのでしょうか?「まずはゆっくり深呼吸することをおすすめします。苦しくならない程度で、例えば6秒吸って、6秒息を止めて、6秒かけてゆっくり吐き出す。これを何度か繰り返し、もし何か別のことが頭をよぎるようであれば、呼吸に合わせて数をカウントすると、次第に心が落ち着いていきます」
それでも再入眠できず、眠れないことでイライラしてしまう場合は、「一度布団から出るのもいいでしょう」と中村先生。できれば電球色系の照明や間接照明の中で雑誌をパラパラめくったり、落ち着く香りを嗅いだり、ストレッチをしたり。
「寝なくちゃいけないと焦ってしまうと、身体がより緊張状態を高めてしまうので、眠ることよりもリラックスして過ごそうと開き直ることも大切です。だからといって、興奮状態になりやすいスマホやゲームをして過ごすことはおすすめしません。読書であっても興奮してしまうようなストーリーは避け、あくまでもパラパラと眺められるものがいいですよ」
■眠れないときにできる対処法を知りたい方はこちらの記事もチェック!
https://www.nishikawa1566.com/column/sleep/20180212110000/
明日のことは明日考えよう
若者の中途覚醒・早朝覚醒の大きな原因の1つになっているストレス。そろそろ寝ようと思っても、仕事モードからリラックスモードに切り替えるには1時間以上のゆとりが必要です。
仕事を終える時間を決めて、スマホはカバンの中にしまって見えないようにしたり、パジャマに着替えたり、気持ちの切り替えがとても大切。
「明日これをやらなきゃと不安に駆られてしまうと、どんどん眠れなくなってしまいます。明日のことは明日考えようと、いかに開き直れるか。たとえば、よほど緊急でない限り、夜19時以降は仕事をしないと決めておく。そのことをあらかじめ仕事仲間や取引先へ伝えておくのもいい対策でしょう。
また、寝不足の状態では仕事や生活のパフォーマンスが低下します。そのため、仕事の効率を下げないためにも、十分な睡眠時間、つまり7時間睡眠を確保するために『1日を24時間ではなく、7時間の睡眠時間を引いた17時間だと思って計画を立てよう』とおっしゃる方もいます。
さらに寝る前の入浴を含めたクールダウンの時間を2時間程度みておく。すると、1日で使える時間は15時間程度です。この15時間を、仕事、家事、趣味活動などにどう配分するか。このように調整していくことが、いい生活リズムをつくるうえで大切だと思います」
***
たとえ眠りにつけなくても、途中で目が覚めてしまったとしても、快眠テクニックを次々に試すのではなく、焦らず、思い悩まず、「考えても仕方がない」「明日のことは明日考えよう」と開き直って、気持ちを落ち着かせることが大切です。
たとえば、寝る前にヨガやストレッチをする、ノンカフェインのハーブティーを飲むなど、寝る前に気持ちが落ち着くことを習慣にするのも良いでしょう。

青山・表参道 睡眠ストレスクリニック院長
中村真樹先生
日本睡眠学会専門医。東北大学医学部卒業、東北大学大学院医学系研究科修了後、東北大学病院精神科で助教、外来医長を務める。その後、睡眠総合ケアクリニック代々木院長を経て、2017年「青山・表参道 睡眠ストレスクリニック」を開院。臨床と研究、両面の実績があり、睡眠に悩む多くの患者さんの治療にあたっている。ビジネスパーソン向けの書籍『仕事が冴える眠活法』(三笠書房)も話題に。
https://omotesando-sleep.com/
この記事を見た人は
こんな商品に興味を持っています
眠りの関連記事
人気記事ランキング
おすすめ記事
最近見た商品
この記事に関連するキーワード
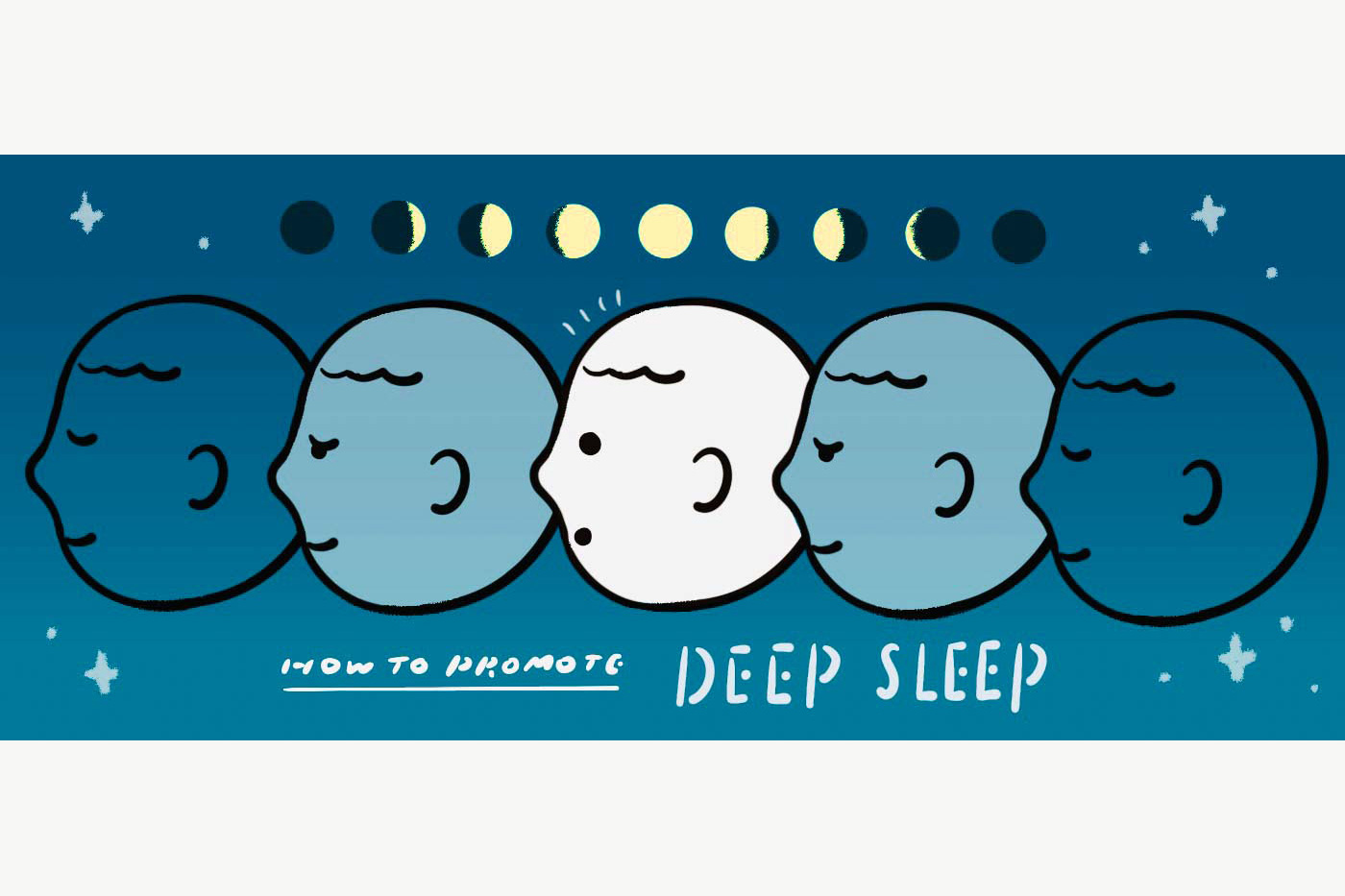
この記事が気に入ったら
いいね!しよう