専門医が銭湯・サウナの健康に良い入り方を伝授!必須の持ち物とサウナハット&サウナマットも紹介
2024.10.31
知る

一過性のブームを超え、勢いの止まらない、銭湯とサウナ人気。休日のリフレッシュはもちろん、日常的に銭湯やサウナに通う人もいるのではないでしょうか?
しかし、利用の仕方を間違えると、命に危険が及ぶことも。健康のためにと銭湯やサウナに通っていたのに、逆に健康を損なってしまったとしたら、そんな残念なことはありません。
そこで、今回、ご登場いただくのは、温泉療法専門医である東京都市大学の早坂信哉先生。
医学の視点から銭湯(浴槽入浴)・サウナの効果をひも解くとともに、正しい入浴方法から“ととのう”のメカニズムをお教えいただきます。
さらには銭湯・サウナ好きがおすすめする必須の持ち物とおすすめのサウナハット&サウナマットまで、銭湯・サウナをより健康的に楽しむためのトピックスをお届けします。
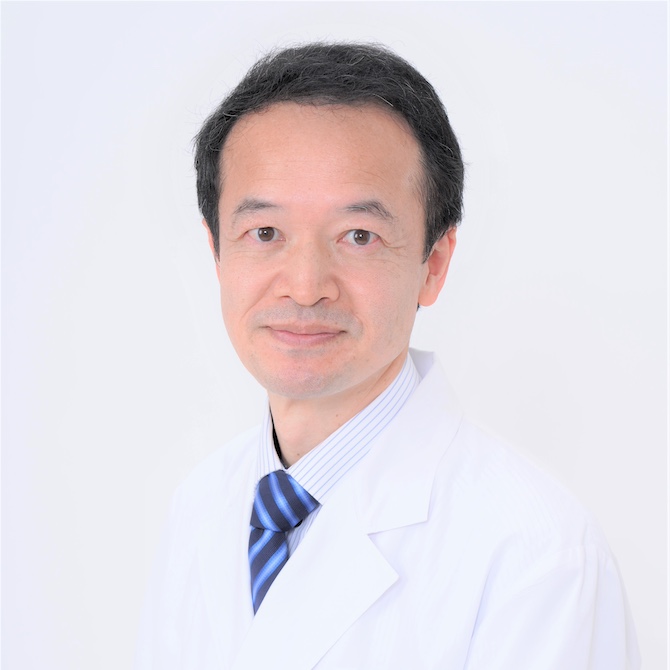
温泉療法専門医
早坂信哉先生
自治医科大学医学部卒業、2002年自治医科大学大学院医学研究科修了後、浜松医科大学准教授、大東文化大学教授などを経て、東京都市大学人間科学部教授。入浴、温泉、サウナ、岩盤浴といった温熱浴に関する研究を25年以上にわたって続け、メディア出演も多数。著書に『おうち時間を快適に過ごす 入浴は究極の疲労回復術』(山と溪谷社)などがある。
自治医科大学医学部卒業、2002年自治医科大学大学院医学研究科修了後、浜松医科大学准教授、大東文化大学教授などを経て、東京都市大学人間科学部教授。入浴、温泉、サウナ、岩盤浴といった温熱浴に関する研究を25年以上にわたって続け、メディア出演も多数。著書に『おうち時間を快適に過ごす 入浴は究極の疲労回復術』(山と溪谷社)などがある。
感覚だけじゃない!医師がひも解く、銭湯・サウナの健康効果
銭湯もサウナも、入浴後には心も体もすっきり。リフレッシュするような感覚を覚える人は少なくありませんが、それだけでなく、医学的に認められた効果もあるようです。
「銭湯にしてもサウナにしても、最たる効果は温熱作用による血流改善です。銭湯やサウナの温熱によって体が温まると血管が拡張し、体内に血液が巡りやすくなります。
すると、改善された血流にのり、体内に37兆個あるといわれる細胞の隅々にまで、栄養分や酸素が届きやすくなります。栄養分や酸素を受け取った細胞はそれらをエネルギーに分裂し、新たに生まれ変わります。つまりは、新陳代謝が促進されるのです。
一方、体内の老廃物を肝臓や腎臓に運ぶことも、血流の大事な役割です。肝臓は老廃物を無毒化し、腎臓は老廃物を排出する働きを持つため、これらの働きが促進されると老廃物が体外に排出されやすくなり、疲労回復やだるさの改善につながります」
そう、あのリフレッシュ感は、たっぷりと汗をかいた爽快感だけにあらず。温まった体の内側では血流が改善され、細胞の生まれ変わりも老廃物の排出も促進されているのです。
「また、銭湯やサウナにはリラックス効果も謳われていますが、これには自律神経の働きが関係していると考えられます。40℃以下の湯船やぬるめに設定されたサウナに入ると自律神経のスイッチが副交感神経のほうへと切り替わり、リラックス状態になるのです」
早坂先生が指摘する自律神経は交感神経と副交感神経の2種類から成り、一方が優位に働くともう一方の機能が低下。つまりは、シーソーのようなバランス関係を持っています。
なかでも副交感神経が優位に働くと心も体もゆったり、リラックスモードになりますが、ぬるめの銭湯やサウナが自律神経の切り替えを促している、というわけです。
「副交感神経のスイッチが入ると筋肉の緊張がゆるみ、神経の過敏性も抑えられることから、ぬるい銭湯やサウナに入ることは筋肉痛や神経痛の緩和にも効果的です。
さらに、睡眠へのメリットもあります。40度のお湯に10分入ると、入浴後には体温が0.5度から1度くらい上がります。1時間半くらい経過すると深部体温が下がり始めるため、このタイミングでお布団に入るとよく眠ることができます」
それだけでなく、広々とした銭湯は「視覚的にもリラックス効果をもたらします」と早坂先生。また、湯船の浮力によって体重が10分の1にも軽くなることから気分まで軽やかに、さらには湯船の水圧により、特に下半身のむくみ解消にも期待できるといいます。
「しかし、銭湯やサウナが持つ温熱作用が、時に健康を損なうことにもつながります。特に温度の高く設定されたサウナから一気に水風呂に入ることは避けるべきです。
なぜなら、41℃以上の湯船や温度の高いサウナに入浴すると副交感神経とは反対に交感神経のスイッチが入り、心拍数や血圧が上昇。血流改善には効果的ですが、間髪入れずに水風呂に入ると拡張した血管が一気に収縮し、ヒートショックを起こす危険性があります」
ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が乱高下し、心臓や血管の疾患が起こること。熱い銭湯やサウナから一気に冷たい水風呂に入ると同様のことが起き、心筋梗塞や不整脈、脳出血や脳梗塞の発作が生じることもあるというから侮れません。
入浴後のお楽しみも!銭湯の正しい入り方をチェック
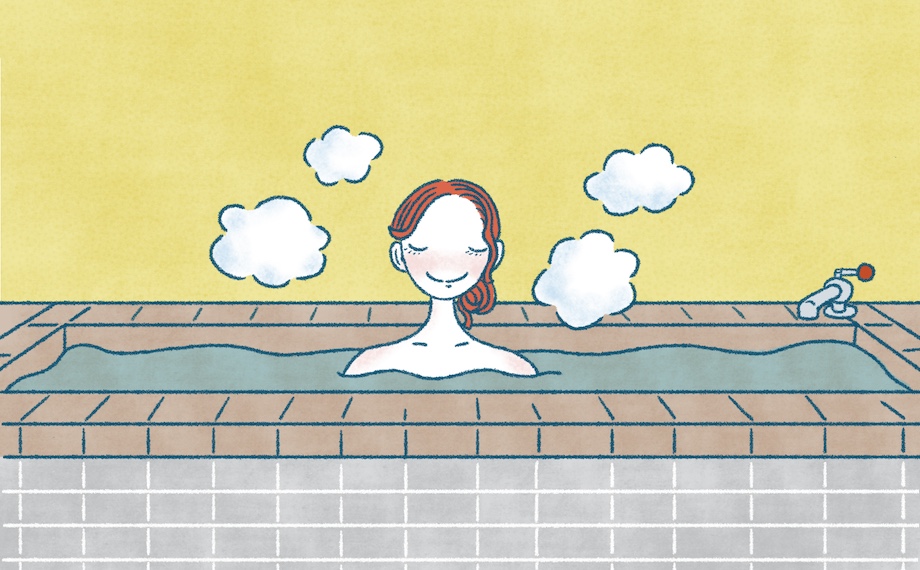
銭湯やサウナを気持ちよく楽しむためにも、ヒートショックのような症状を引き起こさないためにも知っておきたいのが、それぞれの正しい入り方。
まずは、銭湯の正しい入り方からチェックしていきましょう!
①すぐに湯船には浸からず、まずはかけ湯を。
いきなり体の中心にお湯をかけると血圧が一気に上昇するため、最初は体の末端である手足からスタート。安全に湯船に浸かるための準備を整え、なおかつ、体の汚れを落とすため、桶10杯程度のかけ湯が目安です。
②最初の湯船は38〜40℃のものをチョイス
いくつもの浴槽を楽しめることも銭湯の醍醐味。複数の湯船に浸かる場合は、まずはぬるめに設定された38〜40℃程度の浴槽に浸かり、徐々に温度を上げていくと安心。また、サウナやジャグジー風呂に入る場合も、ぬるめの浴槽に浸かってからにしましょう。
③湯船から出たらゆっくり水分補給
血流改善やリラックス効果が期待できる銭湯ですが、湯船に浸かった体は少なからず疲労しています。湯船から上がったらすぐに銭湯を出ることはせず、コーヒー牛乳やお水でも飲みながら水分補給をして、待合スペースで30分ほどの休憩を取りましょう。
「銭湯は“みんなのお風呂”。かつては交流の場としても親しまれていました。その歴史にならい、居合わせた人たちとのコミュニケーションを楽しむのもおすすめです。交流という銭湯の文化を楽しめたなら、30分の休憩もあっと言う間ではないでしょうか」
また、複数の浴槽に浸かる場合には「1回につきトータル10分、長くても15分程度の入浴を目安に」と早坂先生。
先生は研究を目的に1日にいくつもの温泉を巡ることがあるといいますが、その際には「1カ所につき、1分程度で上がることも珍しくありません」だそうです。
“ととのう”の真相を知る、サウナの正しい入り方をチェック
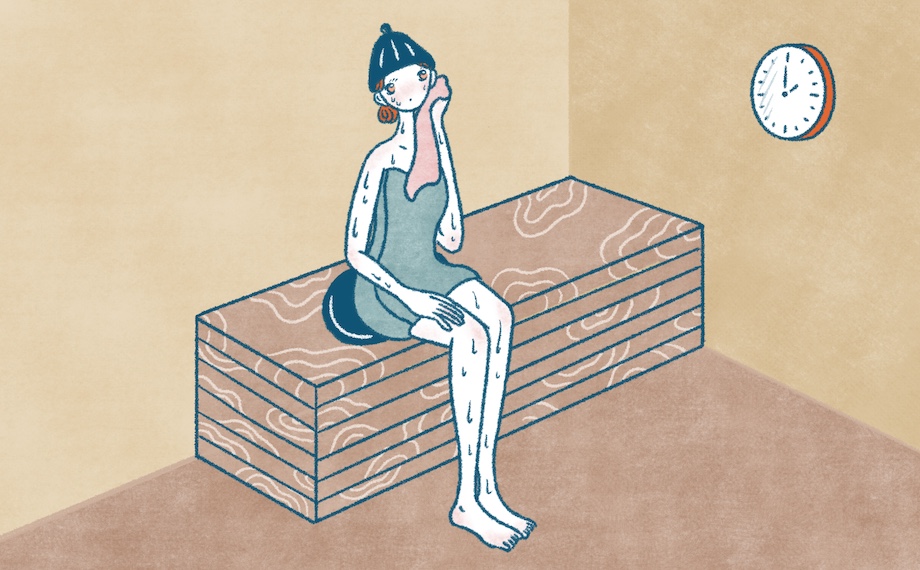
次にチェックするのは、サウナの正しい入り方!
なかには100℃を超えるようなサウナもあるため、銭湯以上に体の状態に注意しながら利用する必要があります。
①入る前に水分補給
サウナに入ると大量の汗をかくため、まずは水分補給から。これを忘れると脱水症状に見舞われかねません。少なくともコップ2杯分程度の水を飲むようにしましょう。
②ぬるめのシャワーで体の準備
銭湯のかけ湯と同様、サウナ前にはシャワーが必須。ぬるめのシャワーによってサウナに入る体の準備を整え、同時に体の汚れを落としましょう。そして、シャワー後には体をしっかりと拭くこと。体に水滴が残っていると、サウナ室の湿度が変化してしまいます。
③初心者は下のひな壇から
サウナ室に入ったら、最初はひな壇の下段に座るのが安心です。温度の高い空気は上に向かうという特性があるため、ひな壇の下のほうが温度が低い傾向にあるからです。特にサウナ初心者の人はひな壇の最下段から始め、徐々に体を慣らしていきましょう。
④汗ばんできたら退出を
設定温度の違いはもちろん、個人差や体調による差が大きいため、サウナに目安となる入浴時間はありません。けっして無理はせず、体が汗ばんできたら退室のサインです。
⑤水風呂の前には必ずぬるめのシャワーを
サウナ室から退出したのち、すぐに水風呂に向かうのは禁物。急激な温度変化により、ヒートショックを起こす危険性があります。そのため、水風呂の前にはぬるめのシャワーかかけ水を浴びること。汗を流すというマナー面だけでなく、体のためにも重要なプロセスです。
⑥外気浴の最中に水分補給を
水風呂から出たら体をしっかりと拭き、最後の仕上げの外気浴へ。しかし、外気浴の前か、外気浴の最中に水分補給は必須。汗として流れた水分をしっかり補いましょう。
「サウナ、水風呂、外気浴の流れを1セットに、これを2、3回繰り返すのが一般的なようですが、あくまでもサウナの効果は温熱作用によるもの。水風呂の冷たさが苦手な人やサウナで疲れを感じた人は、無理をして水風呂や外気浴をする必要はありません」
“ととのう”は体への負担がないとは言えない
多くのサウナ好きを魅了する“ととのう”という感覚は、サウナ、水風呂、外気浴の流れをしっかりと踏むと味わえると聞きますが、実際に体ではどのようなことが起こっているのでしょうか?
「まさに今、研究を進めている最中ではありますが、“ととのう”という感覚にも自律神経の働きが関係しているようです。熱いサウナと冷たい水風呂という強い刺激によって交感神経を優位に働かせた直後に、外気浴によって一気に副交感神経を優位に働かせる。
つまりは、交感神経と副交感神経の極端な切り替えを促すことにより、えも言われぬ心地良さを味わえるのでしょう。しかし、体に負担がないかというと、保証はできません」
それでも“ととのう”感覚を味わいたいなら、無理も我慢もせず、けっして急がないこと。熱さを我慢することなくサウナ室から退出し、水風呂に一気に飛び込んではNG。外気浴をするにもきちんと水分補給をし、寒さを感じたらストップすることが大切です。
銭湯・サウナに欲張りは禁物。暑さに耐え続けるのではなく、ご自身の体調と向き合いながら気持ち良い程度で入浴するようにしましょう!
銭湯・サウナ好きに聞く!より銭湯・サウナを楽しめるアイテムは?
無理は禁物の銭湯やサウナですが、正しい入浴方法を実践すれば、健康的であり、さらにはリラックスが待ち受けつつも心躍るアクティビティでもあります。
銭湯やサウナを日常的に楽しむ方は、持ち物にも一家言ある様子。そこで今回は、銭湯・サウナ好きの方に必携品と気になっているアイテムを伺いました。
週1回は必ず銭湯・サウナに通うという26歳女性・Aさんの必需品は?
「濡れたタオルや洗面用具を入れるのにぴったりな『メッシュバッグ』。ビニールバッグよりも手入れがしやすいので、おすすめです。
また、サウナでは熱で髪が傷んでしまうので、洗い流さないヘアトリートメントを常備しています!
衛生面も気になるところなので、サウナマットも気になっています」
リラックスするのに月2回銭湯・サウナに通う27歳男性・Bさん。
「細長く、厚手のフェイスタオルはいろいろ活用できるので必需品です。サウナハットやバスタオル代わりにもなりますし、外気浴をする前にきちんと水を拭き取る際にも便利です」
お気に入りの銭湯・サウナに週1で通うという26歳男性のCさん。
「最近のお気に入りはスカルプブラシ。洗髪の際に使って優しく頭皮をマッサージすると、ツボ押しのように使えてなんだか疲れも取れるように感じます。
今後あれば買いたいなと思うのが、鼻まで覆えるサウナハット!鼻の粘膜が弱いので、熱から守るのにそういったものがあれば欲しいですね」
疲れたときは必ず銭湯・サウナに通う31歳女性のDさんのおすすめグッズは?
「熱から頭皮を守るサウナハットは必ず持っていきます!あるとないとでは髪の傷み具合も違うような気がしています。
また、入浴後に開いた毛穴に浸透するようにシートパックを持っていくことも。パック使用禁止の施設もあるので、事前に確認してから使用しています」
快適に過ごすために工夫されている銭湯サウナ好きの方々。
これから銭湯・サウナ通いを始めてみたい!という方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
おしゃれに頭と皮膚を守る、nishikawaイチオシの<PEANUTSのサウナハット&サウナマット>
サウナーが必須アイテムとして挙げたサウナハットは、頭皮や髪の毛を熱から保護する役目を担います。なかでもnishikawaの<ピーナッツ サウナハット>は吸水性の高いタオル生地、なおかつ、顔を覆うような深めのシルエットが特長です。
これには早坂先生も「頭皮や髪の毛だけでなく、顔の皮膚も熱の影響を受けるため、私がサウナに入る際には手拭いを頭からかぶるようにしていますが、深くかぶれるサウナハットならおしゃれに代用でき、タオル生地ならお手入れも簡単ですね。入浴の質を上げるには、吸水性のあるタオルを使うことも大切です」と太鼓判。

サウナにおすすめグッズ
自分専用の銭湯やサウナセットを準備したなら、いざ、お目当ての施設へ。
そして、実際に銭湯やサウナの効果を実感したなら、その後のお楽しみにぐいっとビールを想像する人も少なくないはず……!
「銭湯やサウナ後の1杯、おいしいですよね。ただし、アルコールには利尿作用があるため、水分補給にはなりません。また、体が温まった後は血行が促進されているため、酔いも早くなります。そのため、お酒を楽しむにはチェイサーを忘れないようにしてください」
温浴後の1杯を含め、今回お届けした正しい入浴方法を実践し、銭湯やサウナの気持ちよさも健康効果も、めいっぱい味わってくださいね!
Illustration | Mariwa
Photo | ryo tsuchida
Text | Kyoko Oya


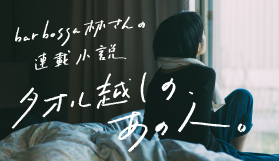






吸水性に優れた今治産のタオル生地。軽くてコンパクトに折り畳めるため、持ち運びにも便利です。サウナを楽しむスヌーピーをデザインした刺繍がキュート!